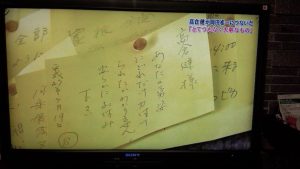10月2日、父が亡くなりました。行年86才でした。
生前、お世話になりましたみなさまには父に代わりまして厚く御礼申し上げます。なお、亡父の葬儀は家族・親族にて執り行いました。このたび四十九日の法要が済みましたので、今回は父のことを書きます。
3年前に脳梗塞になってからというもの、認知症も進み、父のからだは徐々に弱っていきました。退院して自宅に戻りましたが、杖を使わなければたちまち転びそうになるなど、足腰の衰えは誰が見ても明らかでした。ある日、案の定、散歩中に転倒。救急車でふたたび病院に入院しました。そして、運ばれた病院の検査で偶然「膵臓腫瘍」が見つかりました。その「膵臓腫瘍」は良性か悪性かははっきりしなかったものの、若いころに患った肺結核のせいでほぼ片肺状態だった父は手術ができませんでした。入院先の主治医は「ここまで早いステージで見つかることはあまりなく、肺に問題なければ手術をお勧めするところですが」と言ってくれましたが、年齢を考えれば仮に手術が可能であってもしなかったかもしれません。
「膵臓腫瘍」と診断された病院で主治医からの説明を受けた後、すでに購入してあった墓を掃除に行きました。なぜそんなことを思い立ったのかわかりません。この墓は購入してからそのままに放置されており、さぞかし埃をかぶっているだろうと思ってのことでした。でも、お墓は霊園の人が手入れをしてくれていたのか思いのほかきれいでした。一緒に行った長男とふたりで墓石をふきながら「この墓にもうじき父親が入ることになるんだろうか」などと考えていました。いずれにせよ、膵臓腫瘍の手術をしないという選択をしたこともあり、急性期の病院に入院していた父は別の病院に移らなければなりませんでした。私は自宅で母が面倒を看られるようになるまで父を入院させてくれる病院を探しました。
次の病院に移った直後に不思議なことがありました。「腫瘍が消えてしまった」というのです。この病院の外来に来ている膵臓腫瘍の専門医も「腫瘍はない」という意見でした。自宅に帰ってこのことを家族に伝えると、一緒にお墓を掃除した長男が「お墓をきれいにしたからかな?」と。入院中、何回か腹部CTをやりましたが、やはり父の膵臓に腫瘍はないとのことでした。この病院もまた療養型の病院ではなかったため、膵臓に腫瘍がないということになればいつまでも入院しているわけにはいきません。結局、グループホームに入ることになりました。自宅を離れてグループホームで生活することを父がどう思っていたのかわかりません。しかし、自宅で父親の面倒を看る母親の体調もときに思わしくないため仕方ない選択でした。
幸い、介護のプロのみなさんの力をお借りして、父も施設で穏やかに過ごすことができました。しかし、このころの父はほとんど歩けず、介助なしでは食事すらできなくなっていました。そして、突然、心不全となって再入院となりました。入院直後の父は酸素マスクをつけられ、苦しそうな呼吸をしていました。でも、治療によって病状は落ち着き、大好きな羊羹をもってきてくれとせがむまでに回復。とはいえ、すでに嚥下ができなくなっていたため、口からの飲食が禁止されて点滴のみという状態になりました。急変時の対応を確認する主治医には「蘇生は必要ない」、「苦痛を取り除くことを優先し、積極的な治療は望まない」という希望を伝えました。次第に黄疸と熱がではじめ、肝機能も悪くなりましたが、最小限の治療で経過を見るのみでした。
その後、父は少しづつ衰弱していきました。病室に見舞いに行っても、ほとんど話しをしなくなりました。黄疸が強くなり、どんどん痩せていく父。家族みんなでお見舞いにいっても、声を出したり、目を開けたりすらしなくなりました。それは父の最期が近づいている証拠でもありました。しかし、そうした父親の変わりようを目の当たりにしても私には淋しさや切なさ、悲しさや寂寥感といった情感は湧いてきませんでした。自分が薄情だからだろうかとも考えました。祖父が亡くなったとき、あるいは叔父が亡くなったときには涙をこらえることができなかったというのに、父親の死を目前にしてもなお淡々としていられる自分が不思議でした。「もしかして“若いころの父親”に復讐しているのだろうか」と思ったりもしました。
若いころの父はとても厳しい人でした。自分にも厳しい分、家族にもとても厳しい人でした。きれい好きで、家の中が散らかっていると仕事から帰宅したばかりであっても怒りながら掃除機をかけたりしていました。父はまた、外で嫌なことがあると家族に当たり散らす身勝手な人でもありました。子どもの頃の私は帰宅した不機嫌な父親が怒り出さぬよう家中を掃除をして回ったものです。それでも父は「掃除をしていない」と怒鳴り散らし、ときに手を挙げることさえありました。そんな気難しくて自分勝手な父でしたから、一緒に遊んでもらったり、勉強を見てもらったりといった思い出は私の中にはありません。若いころの父は、歳をとるにしたがい丸くなっていった晩年の父からは想像できないほど怖い存在でした。
「辛かった子供時代」を振り返ると父の嫌な思い出ばかりが浮かんできます。警察官だった父はストレスフルな仕事から解放されても、そのストレスを解消することができずにそのはけ口を家庭に求めたのです。父親が帰宅する時間が近づいてくると、いつも不安な気持ちになったものです。月に何回かある父の宿直の日だけは、どんよりとした気持ちから解放されホッとしていたのを思い出します。あのどん底の高校生時代にも嫌な思い出があります。もがき苦しみながら必死に英語を勉強して受験した大学にあえなく不合格だったときのこと。予想はしていたとはいえ落胆していた私に父は「ダメなやつだな」と心ない言葉をあびせました。父なりの叱咤激励だったのかもしれませんが、さすがにこの言葉に私は打ちのめされました。
そうした子供時代、あるいは青年期を過ごしてきたせいか、自分にとっての父の姿は、年老いて穏やかに微笑んでいる父ではなく、かつての厳しくて自分勝手でいつも不機嫌だった父親なのです。だからこそ、父親が今まさに最期を迎えようとしているときにでさえも、喪失感のような淋しさを感じないのではないか、そう思っていたのです。そんな私を見ていた長男が、あるとき私に尋ねました。「父ちゃん、父親を亡くすときの気持ちってどういうもの?」と。私は息子にこう聴かれてハッとしました。それまであまり深くは考えていなかったからです。でも、この息子からの突然の問いかけに、今まで感じてもいなかったこと、思い出しもしなかったことが次々とあたまに浮かんできました。私は、息子に次のようなことを話しました。
****** 以下、息子に話したこと
子どもの頃は本当に大変だったんだよ。もっと大変な子供時代を送った人もいるだろうけど比較の問題じゃないからね。俺がどれほど苦しかったかは誰にもわからないだろうな。そんな苦しい中でよくここまで頑張ってきたなって自分で思うもの。そうした思いが強い分だけ親父を恨んでいたのかも。あからさまにそう感じていたわけじゃないけど。親父が死のうとしているのに喪失感というものがないのは「オヤジへの恨み」があるからじゃないかってつい最近まで思ってた。でも、今はそうではないかもって感じるようになってきたんだ。ほら、以前、親父は君たちに「お前たちのお父さんはすごい人なんだぞ」って何度も言ってたでしょ。何度も何度も「すごい人なんだぞ」って。あれって、ひょっとして俺に謝っていたんじゃないかって思うんだよ。親父はこれまで俺をほめたことなど一度もなかった。「頑張れよ」の励ましの言葉さえもね。その親父が君らに繰り返し「お前たちのお父さんはすごいんだぞ」と言うのを聞くにつれて、俺にはだんだん「昔の自分を許してくれ」って親父が謝っているように聴こえてきたんだ。
****** 以上
そういえば、まだ父が元気だったころ、母が昔のとんがっていた頃の父親の思い出話しをすると、父は「昔のことは言わないでくれ」と話しを遮ったそうです。家族に当たり散らしていた若かった頃の自分を思い出すことは、あの親父にとっても辛いことだったのかもしれません。そんな父が、子供時代の苦労や苦難を乗り越えて医者になった私をどう見ていたのか。それを尋ねてみたことはありません。しかし、老いていく父を目の当たりにした私は、その答えが「お前たちのお父さんはすごい人なんだぞ」という父の言葉にあるのかもしれないと思うようになったのです。そうした「すごい人なんだぞ」という言葉は、きっと私に向けられた父親なりの詫び方だったのではないか。私は次第にそんな受け取り方をするようになっていきました。
あれほどきれい好きだった父が、晩年、脳梗塞の影響か、はたまた認知症が進んだからか、ボロボロと口からものをこぼしながら食べるようになりました。いつも手元に布巾を置き、魚も身と骨をきれいに分けて食べていた父が、まるで餓鬼が食べものにしゃぶりついているかのような光景でした。そんな父を見て、私はあきれたように「どうしてこうなっちゃんたんだよ、オヤジ」と笑うと、父もまた私を見てゲラゲラ笑い出しました。私と父につられて母も笑いました。父親をふくめて三人で笑うなんて何年ぶりでしょう。今までなかったことかもしれません。私はなぜかホッとした気持ちになり、「これでいいんだ」と思いながら目から涙がこぼれそうになりました。その涙に父に対するわだかまりが消えていくのを感じていました。
父親がそろそろ臨終を迎えようとしているとき、家族みんなで病室に見舞いにいきました。父親は顎で大きく息をしながら目を閉じています。いよいよその時がやってくるのです。でも、そんな気配を感じながらも病室に沈痛な雰囲気はありませんでした。私も、母も、妹も、家内も息子たちも、みんな淡々と父の最期を迎えようとしていました。私は父のまなじりにたまっている涙をふいてやりました。そして、まばたきもせずにうすくあいている眼を閉じてやろうとぬらしたティッシュをあてると父は「余計なことをするな」というように顔を横にふりました。「まだまだ元気はあるみたいだね」。嫌がる父を見ながら一同が笑いました。ベットに横たわる父を中心に、家族みんなが自宅にいるようなそんな錯覚におちいるほどでした。
その二日後、父は黄泉の国に向けて旅立ちました。父が亡くなったと妹から連絡があり、診療を中断して病院に行くと、すでに母親と妹、家内が駆けつけていました。しかし、彼女たちには笑顔がありました。私は父の亡骸に近づき、顔にかけられた白布をとると父が安らかな表情で寝ていました。私はまだぬくもりのある父の胸に手を当てながら「お疲れさまだったね」と言いました。涙はありませんでした。喪失感もありませんでした。でも、「お疲れさま」という言葉は、私の本当の気持ちでした。私はその時あらためて思いました。父の死に喪失感を感じなかったのは、父に対する復讐だったのではなく、年老いて弱っていく父を見ながら心から「お疲れさま」と声をかけてあげられる素直な気持ちになれたからではないか、と。
人の人生の価値は「長さ」ではありません。ましてや私の父親のように、自分の思い通りの人生を歩めた人の最期はまさに「お疲れさま」です。三十歳の人生にはその人なりの、六十歳の人生にはその人なりの、九十歳の人生にはその人なりの価値があり、すべての人が「お疲れさま」なのです。若い人の死にはやはり「無念」の思いは禁じえませんが、すべての人の死は残された人にいろいろな形で言葉を残していきます。生きるということはそれらの言葉を引き継いでいくということかもしれませんし、また、「死ぬ」ということはそういうことなのかもしれません。人の死は淋しいものかもしれませんが、必ずしも悲しいものばかりではありません。たくさんの死を見送って来た私は、自分の父親を亡くした今改めてそう感じます。
父の葬儀で私は会葬してくれた親族に挨拶をしました。しかし、その途中、私は涙がこみあげてきてしまい、しばらく言葉がでませんでした。でも、この涙は亡父に対してではなく、挨拶に出てきた祖父の行(くだり)に感極まった結果です。以前にもお話ししたように、祖父は私にとって特別な存在です。祖父が亡くなったときのことを思い出すと今でも涙があふれてきます。会葬者の皆さんは、さぞかし私が父を亡くして傷心しているんだろうと思ったかもしれません。目の前で息子ももらい泣きをしていましたし。しかし、その時の私は父を穏やかな気持ちで見送ることができていたのです。泣いてしまったことを恥じながら、葬儀の後で息子達にいいました。「俺もお前たちに『ご苦労さま』って見送ってもらえるよう頑張るよ」と。
涙で途切れ途切れになってしまった挨拶で、私の言いたかったことが伝わらなかったかもしれません。ですから、改めて会葬者のみなさんへの挨拶を最後に掲載します。
旅だった父に心から「ありがとう」の合掌
************ 以下、葬儀での挨拶
【挨拶】
皆さまには、お忙しい中、父・章の告別式にご会葬くださり、ありがとうございました。
また、〇〇院のご導師さまにおかれましては、父の回向のため、遠くから足をお運びいただき厚く御礼を申し上げます。
父は六月二十日、突然、原因不明の心不全となり、病院に入院しました。
主治医の懸命の治療により一時回復しましたが、もともと膵臓に腫瘍があり、口から食事がとれず点滴管理がつづいたことなどで衰弱が進み、十月二日午前九時五十四分、黄泉の国に向けて旅立ちました。
私も職業柄、いろいろな患者さんを見送ってきました。そして、そのたびに悲しさに涙をこらえることができませんでした。下館のおじいさんを見送るときも、おじさん、おばさんを見送るときももちろんそうでした。
しかし、父の臨終の際には、涙があふれることはありませんでした。また、悲しいといった喪失感もあまり湧きませんでした。
私はふと父への想いを振り返ってみました。
若いころの父は、皆さんもご存知のとおり、とても几帳面で、厳しい人でした。家のなかではいつも不機嫌そうにしており、外で嫌なことがあると、必ず家族に当たり散らす身勝手な人でもありました。
父の仕事が泊まりで、今日は家に帰ってこないという日は、子どもながらにホッとしたものです。子ども時代の思い出といえば、こうしたつらいことが多かったのです。
父の臨終に涙がなかったのは、このようなつらい過去があったからだろうか、と考えたりもしました。
しかし、その一方で、あのきれい好きだった父が、晩年、ぼろぼろと口から食べものをこぼしながら食べるようになり、それまで私たちと面と向かって話しをすることのなかった父が、一緒になって大笑いしながら話しをするようになるにつれ、これまで私の心の中に重く沈んでいたわだかまりが徐々に消えていくのを感じました。
父自身もまた、「昔のことは言わないでくれ」と、若かりしきころの自分を思い出したくない様子もうかがえました。
いろいろなことがあったにせよ、晩年、かつての厳しさはなくなり、少しづつ穏やかに、そして、おおらかになっていく父を目の当たりにしました。
そして、いいことも悪いこともふくめて、父の人生そのものは全体として幸せだったのではないか、自分の人生に満足しながら父は旅立つことができたのではないかと思えるようになりました。
私は今、ひょっとしてこの式場のどこかにいるかもしれない父に、心から「ごくろうさま」と言ってあげたい気持ちがしています。
そう考えると、父の臨終に涙がなかった本当の理由は、実はそこにあったのではないか。つまり、これまでのわだかまりをすっかり清算してお別れをすることができると私自身が確信したからではないかと思います。
これからは、私と妹、家内と子どもたち、みんなで力をあわせ、残された母を支えていきたいと思っております。
しかし、私達もまだまだ未熟ものばかりです。親戚のみなさま、ならびに〇〇院のご導師さまにおかれましては、どうぞ今後とも、ご指導いただければ幸いです。
以上、簡単ではございますが、家族の代表としてご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。