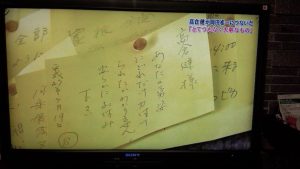この記事は2016年11月20日に投稿されたものですが、最近、この記事にスパムメールが多数送られてくるようになったため、改めて投稿しなおします。なお、元原稿のタイトルは英語でしたが、今度はこの英語のタイトルを頼りにメールを送ってくるようになったので日本語にしました。
********* 以下、本文
このブログを読んでくださっている方はすでにおわかりだと思いますが、私はおさないころから少し変わった子どもでした。テレビっ子だったとはいえ、子供番組よりも大人が見るようなドラマが好きでしたし、子ども同士でわーわー遊ぶよりも一人で遊ぶことを好む子供らしくない子どもでした。今でもはっきりおぼえているのは、私が小学校に上がる前のこと。なにげなく見ていた新聞の大見出しの文字をまねて字を書いてみた私はなにか新聞の見出しと違うことに気が付きました。「なにが違うんだろう」。そう思った私は自分の書いた文字列と新聞の大見出しを何度も比べてみました。そしてついに気が付いたのです。私が書いていた文字列は漢字だけだったということに。当時は漢字もひらがなも同じ文字に見えていたのかもしれません。そこで今度は漢字とひらがなを適当に混ぜて書いてみました。すると今度は新聞の大見出しのように見えてきてすっきり。そんなことをひとりでやっているのが好きな子どもでした。
ですから、友達と遊ぶこともそれほど楽しいとも思いませんでした。たまに私の家に友達が遊びに来ても、友達は友達だけで遊び、私は自分の興味のある遊びをしているということがしばしばありました。親戚の家に行って「みんなでトランプをやろう」と誘われても、興味がないものには「僕はやらない」といって見物するだけということもあったり。親には「みんながやるときは一緒にやらなければだめじゃないか」といわれましたが、やりたくもないことをなぜやらなければならないのか、子どもながらにその理由がわからず納得できませんでした。今思うと、人から「こうしなければならない。こうするのが当然だ」と他人の価値観を押し付けられるのが嫌だったんだと思います。そんな風でしたから、親からは私はいつも「かわり者だ」と言われていました。きっと親戚の人達にも同じように思われていたでしょうね。でも、私の心の中では子どもながらの価値観と言うものがあって、それを否定されたくないと考えていたんだと思います。
そんな私の偏屈なところがふたりの子供達にも引き継がれていて、頑なな性格とわが道を行く姿にはちょっと複雑な思いがします。私がこれまで歩んできた半世紀を振り返ると、子供達が私から引き継いでいるものは決していい面ばかりではないからです。確かに、自分の信念や価値観に忠実だというのも悪くはありませんが、それはときとして他人との価値観の軋轢(あつれき)を生みます。他の価値観とぶつかったとき、調整が必要となる場面でトラブルのもとになるのです。その結果、自分に不利益が生じることだってあります。私自身、これまでそうした場面に何度も遭遇しました。そのときには深く考えませんでしたし、損得勘定で自分の価値観をねじまげるなんてことは考えられませんでしたから。でも、齢(よわい)五十路を超えて、これまでの人生を振り返る年齢に差し掛かると、はたしてそれでよかったのかとときに思ったりします。そして、自分の性格を引き継いでしまった子供達には同じ苦い経験をさせてはいけないと思うのです。その意味で、職場での経験はとても教訓に満ちています。
ある病院に勤務していたときのことです。私は主治医とトラブルとなったある患者を引き継ぐことになりました。そのトラブルに関しては私も詳細を知っていたのですが、このケースはどう考えても主治医に非があることを私は確信していました。しかし、病院は主治医の側に立ってこのトラブルを解決しようとしている。私はそれにどうしても納得できませんでした。上司に呼ばれて意見を求められた私は率直に言いました。これはどう考えても主治医の対応に問題がある、と。すると上司は「君はいったい誰の側にたってものを言っているんだ」と顔を真っ赤にして私を叱責しました。意外だったその言葉をきいて、私は「どちらかの立場に立って発言しているわけではありません。客観的に見て彼に問題があると言っているんです」。私はそう反論しましたが、私の意見はまったく受け入れてもらえませんでした。結局、私はこの一件があって病院を退職することになりました。先輩の医師に「おまえの言うことは正論だよ。でも、言っても変わらないことを言うのは言うだけストレス。辞めるしかないよ」との忠告を受け、それに納得してのことでした。
でも、他の職場に移っても、結局は同じなのです。上司との価値観の対立はもちろん、職場の価値観が合わないっていう場合もあります。要するに、組織とはそういうものなんだと思います。社会に、あるいは組織に身を置くということは、自分の価値観をそうした組織のそれに調整するということなんでしょうね。当時の私はそれを十分に認識することもできませんでしたし、その意志もなかったため、結果的に自分がめざしていた方向性が少しづつ変わってしまいました。大学に残っていろいろやりたかったことがあったにも関わらず、図らずも地元に戻って開業医をすることになったのです。あのときもっと柔軟にできれば、また別の人生を歩んでいたかもしれません。そう思うと、私の性格を引き継いでしまった子供達が私と同じ轍(てつ)を踏まないように…と思ってしまいます。子供が成長して私の話しがわかる年齢となり、かつての私と同じような失敗を子供が繰り返しそうになれば、ことあるごとに自分の性格がどういう結果をもたらしたのか。その結果がどう今につながっているのか。私なりに話しをするようにしていますがなかなか素直に受け入れてもらえませんね。
結局は子供は子供の人生を歩むことになるんでしょう。自分の子どもの頃を振り返ってみても、親の経験談など素直に耳を傾けようなんて気持ちはありませんでしたから。でも、それでいいんだと思います。人間の人生はその人のものであり、その人生の価値など他人が評価するもんじゃないんですから。人がうらやむような人生を送ったとしても本人には満たされなかったこともあるでしょうし、他人にとってはちっぽけでも人知れず幸せな人生をまっとうできた人だってたくさんいるのです。人間の一生なんてそんなもんです。自己満足できればそれでいいんだと思います。だから、私は子供たちには他人の価値観に振り回されることなく、自分の信じる道を歩んでほしいと思っています。私の後継ぎとして医師になってほしいとは思いませんし、一流大学を出て一流企業に入ることが目的になってほしくありません。こうしたことは長い人生においては単なる手段にすぎないのですから。目的はもっと別なところにあるんだと思うんです。自分の力で生き抜くことができ、自己実現できるような人生が理想なんです。
家庭を犠牲にして会社のために突っ走る人もいなければならない。名誉や富を求めて世の中を引っ張っていく人もいなければならない。世のため人のために無私の心で社会に奉仕し、活動する人もいなければならない。そのすべての人の総体が社会なんだと思います。あくまでもその社会の中でひとりひとりが自己実現をしていくことが大切なのでしょうし、私の子供達にもそうしたことに意識的になってほしいのです。勝海舟が咸臨丸でアメリカに渡ったときに感心したことのひとつが、アメリカ人は歴史的な人物の子孫がその後どうしているかにまるで関心がないということでした。日本に戻り、将軍に訪米の感想を尋ねられたとき、このことを話したそうです。そして、「アメリカで偉くなった人はそれ相応に優秀だというところは日本と大きく違うところ」と付け加えることも忘れなかったらしいです。勝のこうしたところが私は好きなのですが、それはともかくいろいろな価値観を認め、個人主義・自由主義を守るために国民が一致団結するところがアメリカのいいところなんだと思います。「和して同せず」って奴ですね。
これまでの自分の人生を振り返ると、運命的な人との出会いがあったからこそ今があると思います。機会があればそのあたりのことも書きますが、こうした人から問いかけられたことが今につながっていると感じます。生きるってことはそういうことなのかも。つまり、自分自身に突き付けられた人生の転換期に、いかに冷静に答えを見出すか。そのために、いかにして運命的な出会いに気が付くか、ということ。人間は悩めば悩むほどものごとを深く考えることができます。ものごとを深く考えればその意味になんとなく気が付きます。その積み重ねが生きることなのでしょう。なにが幸せで、なにが不幸かではなく、なにに価値があり、なにに価値がないということでもない。いいことも悪いことも、心地よいことも不快なことも、全部をひっくるめてその意味に気が付くこと。それが深く生きることなんだと思います。そして、神の定めた寿命が尽きるとき、自己実現できたかどうかに結論がでればそれでいい。たくさんの生老病死を身近に見てくると、「人生は気楽にいこうぜ」だってつくづく思います。