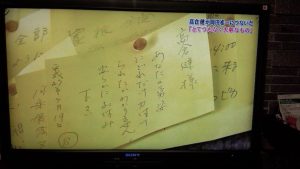この記事は平成28年11月に投稿されたものですが、またまたスパムメイルが集中してきたため同じ内容のものを改めて投稿し直します。以下、その記事です。
ミシガン大学との共同研究のためにアメリカに行かなければならなくなったとき、実は家内はあまり乗り気ではありませんでした。英語を話せるわけではありませんでしたし、なにより海外旅行にも行ったことがなかったので不安だったのでしょう。だからといって家内を日本においていくわけにもいかず、家内を説得してなんとかアメリカ行きを納得させたのでした。
アメリカに行くことが決まると家内は英会話を勉強し始めました。ネイティブスピーカーの先生のいる英会話教室に通い、英会話の通信教育を受講して滞在中会話に困らないよう準備しようというわけです。私も英会話に困らなかったわけではありませんが、英語を話さなければならない状況に追い込まれなければいくら事前に勉強しても使いものにならないだろうと思ってさしたる準備はしませんでした。
その私の考えは間違っていませんでした。日本でやったことなどほとんど役に立たず、実際にアメリカ人を相手に冷汗をかきながら話しをし、苦労しながら英語でコミュニケーションをとらないと英会話は身に着かないことを実感しました。アメリカに渡っていつも英語を話さなければならくなった当初、私は寝言を英語で言っていたそうです。それだけ頭の中を英語が駆け巡っていたんだと思います。
当初は英会話に苦労するのではないかと心配していた家内も、買い物をするときのやり取りに困らなくなるとどんどんと英語が聞き取れるようになっていきました。日本に戻ってくるころには私よりも聞き取れるようになっていて、家内の上達ぶりは目を見張るものがありました。私はといえば、なんとか自分の言いたいことを言えるようになってはいたものの、聞き取りには最後まで苦労していました。
ミシガン大学があるアナーバーから自動車でナイアガラの滝まで旅行した時のことでした。出発したのはまだ陽の登らぬ早朝でしたが、猛烈な雷雨で真黒な雲の表面を稲妻が走り抜けるのをはじめて見て圧倒されました。アメリカの気象の変化はものすごくスケールが大きく、真夏になるとTVの天気予報では「Thunder storm alert(雷雨・竜巻予報)」をやっているほどです。
真夏の強い日差しが照り付けていたかと思っていたら突然真っ黒い雲が出てくるなんてことも珍しくありません。家内と真夏の日差しの中をスーパーに行ったのですが、買いものをしているうちに外がたちまち真っ暗になりゴルフボールほどの雹(ひょう)がボンボンふってきたことがありました。まるで地獄のようなすさまじい光景を目の当たりにして小さな子どもなどはその恐ろしさに泣いていました。
そんな雷雨の中、アナーバーからハイウェイを走ってデトロイトのダウンタウンを抜け、アメリカとカナダの国境へ向かいます。ミシガン大学の共同研究者から「デトロイトの危険なダウンタウンに迷い込まないように注意するんだぞ」と脅かされていたせいか、まわりの風景を楽しむこともできずにカナダ入りしました。万が一スラム街に入ってしまったらどうしよう・・・なんて。
それでも往路はトラブルもなく順調でした。ナイアガラに着くと轟音を立てて流れる滝のスケールの大きさに感動。夜のライトアップされた滝も美しく、それにもまして早朝の太陽に水しぶきがキラキラと輝く滝の美しさはまた格別でした。滝周辺のフラワーランドをまわったり、有名な花時計に立ち寄ったりと、楽しい旅を満喫してミシガンへの帰途に就きました。事件はそのときに起きました。
ミシガンに戻るため、カナダ側から国境に入った私たちの車をアメリカの国境警備隊の隊員が呼び止めました。ナイヤガラの旅を満喫してすっかりご機嫌だった私はこれからなにが起こるかもわからずにいました。私がにこやかに挨拶をするとその隊員はなにか質問をしてきました。その質問は英語のはずなのですが、なにを言っているのかわからない。どこかのなまりでもあったのか聞き取りにくかったのです。
なんども聞き直すうちになんとなく「おみやげをなにか買って来たのか?」と言っているような気がしてきました。私は「なんてフレンドリーな隊員なんだろう」と思いながら、「いいものが手に入ったよ(直訳)。メープルシロップでしょ、帽子でしょ、それと・・・」、にこやかにそう答えて品物を見せる私にその隊員は急に血相をかえて言いました。「車を降りるんだ。今すぐにだっ!」と。
突然のことだったので私は狼狽してしまいました。何がおこったのかさっぱりわからなかったからです。私は隊員に言われるがままに車を降りて事務室に「連行」されました。事務室に入り、机の前に座らされてなにがはじまるんだろうとまわりをきょろきょろしていると、私が得意げに見せた品物をもって隊員がやってきました。彼はあきれたような表情で私に事情を説明しはじめました。
改めて彼の話しをよく聞いてみると、どうやら「カナダ側で知らない人間からなにか荷物をあずからなかったか?」と質問していたらしいのです。その質問に私が「もちろん。メープルシロップでしょ、帽子おでしょ」なんて答えたものですから、私はてっきり麻薬の運び人かなにかと間違われたようです。私の聞き取り能力の悪さが招いたとんだ誤解というわけです。お恥ずかしい話しです。
アメリカ人の友人によれば、アメリカとカナダの国境の警備はそれでも結構ゆるいんだそうです。違法移民や麻薬の密輸が多いメキシコ国境での警備はもっと厳しいとのこと。このときのことがあったからかどうかはわかりませんが、その後、帰りのシカゴ空港でも麻薬の運び屋と疑われ、飛行機に持ち込もうとした荷物の取っ手の部分を中心に検査をされました。麻薬の運び屋には私のような顔が多いのでしょうか。
当時はまだアメリカの安全保障を根底から揺るがした「9.11テロ」の前。とはいえどの空港でも警備は結構厳重でしたから、今では相当厳しい警備がおこなわれているのでしょう。麻薬の運び屋と間違われた私などが今のアメリカに行ったらどうなってしまうんだろうと考えただけでも恐ろしくなります。つくづくなんの不安も持たずに生活できる日本に住んでいることをありがたく思います。
他の国に住み、その国を理解する。そしてその国の人々と交流を深めて友好関係を築く。その意味でも外国語を学ぶことは意義深いと思います。人と人とのきずな、国と国との信頼関係はコミュニケーションからはじまるんだということを痛感します。海外での生活を経験し、海外の文化を知ることで世界平和につながっていくのでしょう。お互いを理解することはとても大切です。
アメリカに行って私はアメリカの懐の広さを知りました。そして、アメリカが好きになりました。と同時に日本の歴史と文化のすばらしさにも改めて気が付いて日本人であることを今まで以上に誇りに思うようになりました。今、このときのことを子供たちに話して、子供たちにも是非海外での生活をさせたいと思っています。アメリカでの生活は私たち夫婦にとってはかけがえのない経験だったなぁと思います。